平成28年12月19日、最高裁判所は過去の判例を変更しました。
その内容はと言いますと、「預貯金も遺産分割の対象となる」というものです。
これまで、預貯金は相続発生と同時に各相続人が法定相続分に従って当然に可分債権として取得するため、遺産分割の対象とならないとされてきました。
ただし、実務上においては、遺産分割調停等でも事実上相続人合意の上で、遺産分割の対象としてきた取り扱いがあります。
しかし、その判例が変更され、「預貯金(普通預金、通常貯金、定期貯金)も遺産分割の対象となる」とされました。
鹿児島での相続相談、相続人調査、遺産分割協議、遺言書作成なら、鹿児島の竹之下真哉司法書士・行政書士事務所へ
相続手続あれこれ
平成28年12月19日、最高裁判所は過去の判例を変更しました。
その内容はと言いますと、「預貯金も遺産分割の対象となる」というものです。
これまで、預貯金は相続発生と同時に各相続人が法定相続分に従って当然に可分債権として取得するため、遺産分割の対象とならないとされてきました。
ただし、実務上においては、遺産分割調停等でも事実上相続人合意の上で、遺産分割の対象としてきた取り扱いがあります。
しかし、その判例が変更され、「預貯金(普通預金、通常貯金、定期貯金)も遺産分割の対象となる」とされました。
| 遺贈(いぞう)とは、遺言者が遺言によってする相続財産の無償譲渡のことをいいます。 (遺言で「この不動産は○○さんにあげますよ」というような場合です) 遺贈は遺言でしかできないため、遺言書がない場合は、遺贈という問題は発生しないことになりますが、もしも遺言書がある場合又はこれから遺言書を作成する場合は、「相続」なのか「遺贈」なのかで色々と注意すべき点がありますので気を付けてください。 |
 |
まず、遺贈は大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類から構成され、各遺贈の性質は全く異なります。(別に「負担付遺贈」というのもありますが、詳細は後述)
そして、遺贈を受ける人(相続財産をもらう人)のことを「受遺者(じゅいしゃ)」といい、相続の場合と異なり会社などの法人も受遺者となることができますし(相続財産を相続できるのは自然人に限ります。)、相続人以外の人が受遺者になることができるのは当然のこと、相続人も受遺者となることができます。
それでは、具体的になにをもって「相続」なのか「遺贈」なのかを判断するかというと、遺言書に記載された文言からというのが原則です。
もっともわかりやすいところで、「この財産を○○に相続させる」とあれば相続となりますし、「この財産を○○に遺贈する」とあれば遺贈となるわけですが、これには例外があります。
【例外】
相続財産を相続できるのは相続人だけです。ですから、相続人以外の人(親しかった友人等)に「相続させる」ことはできないことになります。仮に「この財産を親しかった友人○○さんに相続させる」といった遺言書を書いたとしても、それは「相続」ではなく「遺贈」ということになります。
| 近年、土地や建物などを子どもに生前贈与したいという親が増えてきています。
子どもは相続人ですから、生前贈与しなくとも将来的には「相続」という形で親の財産を取得することになるのですが、その背景には「生きている間に子どもに名義を変えて安心したい」といった親心があるようです。 土地や建物といった不動産を親から子どもへ生前贈与する場合、次の点に注意が必要です。 |
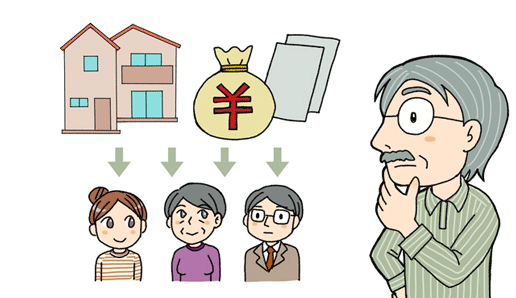 |
| 土地や建物といった不動産を生前贈与する場合、登録免許税の税率は2%ですが、これが相続になると0.4%ですから、相続で名義変更するのと比較すると生前贈与した場合は登録免許税が5倍高くなります。
例えば土地と建物の評価額が合計1000万円とすると 【生前贈与した場合の登録免許税】 【相続した場合の登録免許税】 となります。 |
 |
| 畑や田んぼを生前贈与する場合、その贈与について農業委員会から農地法に基づく許可を受ける必要があります。
しかし、相続の場合だとこの許可が不要になります。 もしも畑や田んぼの生前贈与を考えている場合、農業委員会から農地法に基づく許可を受けることができないときは、相続が開始するまで名義変更はできないことになります。 |
 |
生前贈与する際に一番気をつけるべきは、この贈与税の問題です。
仮に1000万円の建物を生前贈与したとすると、その際の贈与税は次のようになります。
【贈与税】
1000万円-110万円(基礎控除)=890万円
890万円×50%(税率)-225万円(控除額)
贈与税額=220万円
このように贈与税はかなり高額になりますし、贈与税を負担するのは贈与を受けた子どもになりますから、「生前贈与を受けたはいいが、こんなに贈与税を負担するのであれば生前贈与を断れば良かった」などということになるかもしれません。
しかし、次で説明する相続時精算課税を選択することで、生前贈与の際の贈与税の問題はある程度解決することが可能になります。
生前贈与は、その名のとおり「贈与」ですから贈与税が発生する場合が出てきます。
贈与税は多数ある税金の中でも税率が高い税の1つですから、贈与税に気をつけて生前贈与をしないととんでもない税金を支払うことになりかねません。
しかし、生前贈与について一定要件を満たしている場合には控除限度額が2500万円(2500万円までの贈与なら贈与税がかからない)の相続時精算課税を選択することができます。
この相続時精算課税を上手に選択することで、2500万円までの贈与なら、生前贈与する財産に制限無く贈与税を気にせずに生前贈与が可能になるわけです。
相続が開始すると、原則として相続財産は共同相続人の共同所有となります。
しかし、この共同所有状態は一時的な形態にすぎないため、その後確定的に個々の相続財産をどのように各共同相続人に帰属させるかを決めるのが遺産分割協議となります。
共同相続人は、原則として、いつでも、遺産の分割をすることができる。(民法907条1項)
ですから、共同相続人の1人から遺産分割協議の申出があった場合は、他の共同相続人は遺産分割協議をする義務を負います。
仮に遺産分割協議に協力しないときは、家庭裁判所に分割の審判を請求できます。(民法907条2項)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 (民法1028条)
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
遺留分とは、法律が最低限保証している相続人の取り分です。
(続きを読む…)
相続欠格とは、一定事由が発生することにより法律上当然に相続人の資格を奪う制度で、相続人の排除とは違い、被相続人の意志に左右されることはありません。
(つまり、相続欠格者に該当すると、その人は相続人ではなくなってしまいます。ですから、相続欠格者には遺言で財産を残すこともできませんし、遺贈することもできなくなります。(相続欠格者は、受遺欠格者でもある))
たとえ相続人の地位を有する者であっても、その者に相続人としてふさわしくない行為があれば、その者に相続権を認めることは好ましくありません。
そのため、民法上相続欠格に該当する事由として次の5つが定められています。
(続きを読む…)
相続人の廃除とは、被相続人が推定相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が推定相続人にあったときに、家庭裁判所に請求して相続人の資格を奪う制度です。(民法892条)
相続欠格も相続人の相続人たる資格を奪う制度ですが、相続欠格は法律上一定事由の発生により当然に相続権を奪うのに対して、相続人の廃除は被相続人の意志によって相続権を奪うというところに違いがあります。
また、相続人の廃除により被相続人が相続権を奪うことのできる推定相続人は、遺留分を有する推定相続人に限ります。(つまり、配偶者や子供・親などです)
なぜかというと、遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)は、被相続人が遺言書を作成することで、その人に相続させないことができるからです。(例えば、兄弟が相続人となるようなケースでは「全財産を妻に相続させる」とか、「全財産を○○に遺贈する」といった遺言書を残しておくことで、兄弟は相続することができなくなります)
それに対して、遺留分を有する相続人の場合、たとえ遺言書で相続財産を与えないとされていても、法律が保証している最低限の取り分である遺留分がありますから、もし自己の遺留分を主張されれば相続財産を取り返される可能性があるのです。
「相続」というのは相続人の意思とは関係なく、故人の権利・義務をすべて承継するというのが原則です。
相続財産にはプラスの財産(預貯金、不動産等の資産)もあれば、マイナスの財産(借金)もあります。「借金は相続したくないから不動産や預貯金だけ相続する」といったことは残念ながらできません。
相続するときは、プラスの財産マイナスの財産両方を相続する必要があるのです。
ですから、マイナス財産が多い場合は、結果的に借金のみを相続するということになるので、「それだったら相続したくない」ということになると思います。
それでは相続したくないきはどうすればいいのでしょう?
もしも、相続したくないときは「相続放棄」という手続きをとることになりますが、 この「相続放棄」は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述して行います。(通常は亡くなったときの住所地のことで、住民票上の住所地となります)
要するに家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄ができるわけです。
相続放棄には必ず家庭裁判所での手続きを必要とするため、例え「相続放棄します」といった書面に署名及び実印を押していたとしても、法律上の「相続放棄」にはあたらない事に注意してください。
ちなみに相続放棄をする時は、故人の死亡を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しないといけません。
例外もありますが、基本的には三ヶ月であり、この期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。
相続開始後は速やかに相続財産の調査をして、相続放棄をすべきかどうか検討するようにしましょう。
誰かが亡くなって相続が開始しても、その人に必ずしも相続人がいるとは限りません。
天涯孤独で亡くなる方もいるでしょうし、相続人はいたけど相続放棄や相続欠格、相続人廃除等により相続人の資格を失って、相続人がいなくなるという状況もあります。
また、戸籍の消失などで相続人がいるかいないかさえも不明・・・ということもあり得ます。
このように、「相続人がいない」もしくは「相続人がいるかいないのか不明」といった状態を法律上「相続人不存在」といいます。
(実務上相続人不存在となるのは圧倒的に「相続人がいない」ケースです。)
それでは、相続人がいないような相続人不存在の場合、相続財産はどのように扱われるのでしょうか?(通常の相続では、故人の財産は相続人が引き継ぐことになりますが、引き継ぐ人がいない場合はどうするのかという問題です。)
相続人不存在の場合、まず、相続財産は法人とされます。(民法951条)
そして、家庭裁判所で相続財産管理人という人が選任されて、この相続財産管理人が相続財産法人(相続人がいない故人の相続財産)を管理するようになります。(民法952条)
その後、故人の債権者がいるのかどうか、相続人がいるのかどうかを一定期間公告した後、最終的に相続財産は国庫に帰属することになります。(民法959条)
(ここで故人の債権者がいたら、つまり故人がお金を借りていたとすると、貸していた人に対して、相続財産管理人が故人の財産から返済を行ったり、相続人が出てくれば故人の財産は相続人が引き継ぐことになります。)
このような一定の手続きを経て、故人の債権者もいない(債権者がいて返済をしてもまだ財産が残る場合)かつ相続人も出てこないといった場合は、最終的に「相続人がいない故人の財産は国のものになる」ということです。
ただしこれには例外があり、相続人不存在の場合であっても、相続財産が国庫に帰属しないケースがあります。
相続人不存在の場合に、相続財産が国庫に帰属しないケースとしてまずは「特別縁故者への分与」という制度があります。
これらの者を特別縁故者といいます。
特別縁故者は相続人ではありませんが、故人と親族に類似できるくらいの関係にあったということから、これら特別縁故者からの請求により相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えようというものです。(民法958条の3)
もうひとつの例外は、故人が不動産を共有していた場合です。
この場合、その不動産の共有者が故人の共有部分を取得することになります。
あくまでも、共有不動産の故人持分についてのみで、その他の相続財産については特別縁故者が取得するか国庫に帰属することになります。

あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
mail:info@kagoshima-souzokuigon.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab